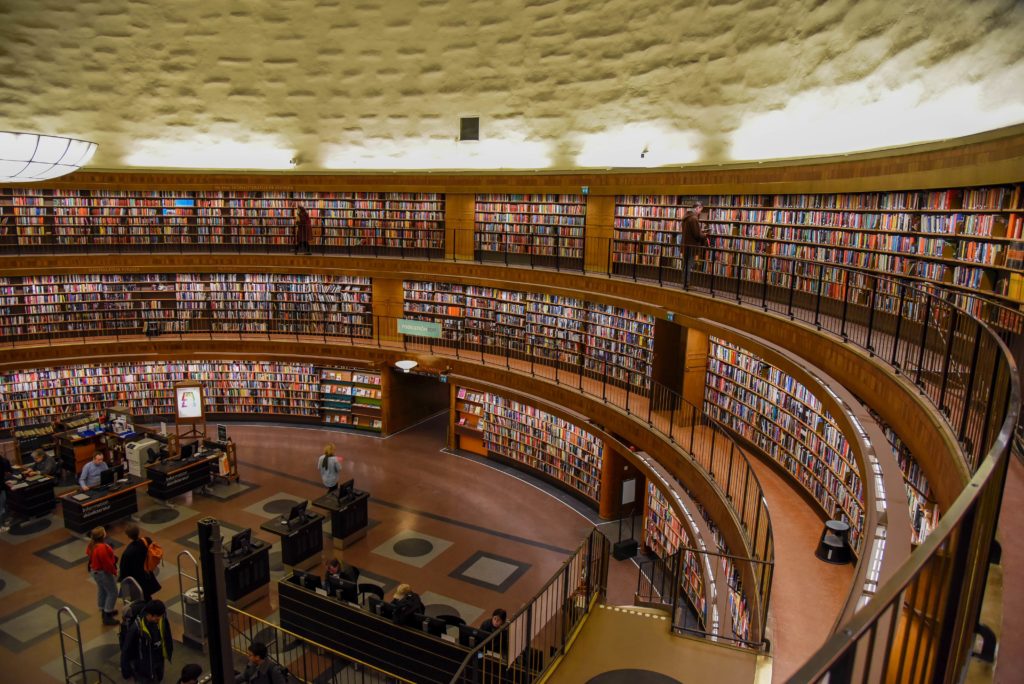

公認会計士予備校の費用を知りたい人「公認会計士を目指すために予備校に入ろうと思う。でも、予備校ってどのくらいの費用が掛かるんだろう?また、どの予備校が一番いいんだろう?」
この記事ではこういった疑問に答えます。
先に結論
予備校の受講料は最も一般的な大手予備校のコースで70~85万円ほど。
毎年、合格者全体の8~9割が大手予備校の受講生で独占されている。
おすすめの予備校はCPA会計学院。理由は①合格者数が圧倒的に多いから②サポートが充実しているから
CPA会計学院を検討するなら、無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです。
こんな人向けの記事です
どの公認会計士予備校に入るか迷っている人
そもそも公認会計士の予備校がどんなところか知りたい人
この記事の信頼性
この記事の筆者は、2年の勉強期間で公認会計士試験に合格しています。
目次
公認会計士試験の概要

先に結論
公認会計士とは会計監査をその専門業務とする資格で、一般的に年収がとても高い。
二次試験(論文式試験)合格が一旦のゴール(高年収の仕事に就けるから)。
公認会計士試験の予備校についてご説明する前に、まずは公認会計士試験の概要についてご説明します。
公認会計士試験~公認会計士資格の取得までの一般的な流れは以下です。
1.公認会計士短答式試験合格
2.公認会計士論文式試験合格(予備校はこれに合格するまでのカリキュラム)
3.会計に関する仕事に就職(公認会計士登録するためには2年以上の会計に関する仕事での実務経験が必要。だからこのタイミングで就職します。)
4.終了考査合格(論文式試験の後、補修所という機関で通常3年かけて講義などを受けて必要単位を取得したら受けられる試験)
5.公認会計士登録
以下で詳細に解説します。
公認会計士とは
公認会計士とはどういった資格かと言いますと、会計監査をその専門業務とする国家資格です。
会計監査とは、簡単に言えば、企業の作成した決算書に誤りや不正が無いかを調べる仕事のことです。
ただ、公認会計士じゃないと会計監査はできないですが、公認会計士の資格を取った人はコンサルや経理責任者などの仕事に就く人も多いです。
そして正直、年収はとても高いです。公認会計士の平均の年収は800~900万円ほどと言われています。
公認会計士試験の概要
そんな公認会計士資格を取得するためには、3つの試験に合格する必要があります。その3つとは短答式試験、論文式試験、修了考査の3つです。
短答式試験は、公認会計士試験の入り口であり、つまり公認会計士試験の一次試験です。年に2回、5月と12月に実施されています。
短答式試験に合格すると、次に論文式試験を受けることができるようになります。論文式試験は年に1回、8月に実施されています。
試験合格後
公認会計士登録するための要件は以下の3つです。
①論文式試験合格
②終了考査合格
③会計にかかわる仕事での2年以上の実務経験
このように公認会計士登録のためには試験だけでなく、実務経験も必要です。
ですので、通常、論文式試験に合格したタイミングでみんな就職します。求人する側の企業も論文式試験の合格のタイミングでリクルートします。この論文式試験合格で8~9割の人は監査法人という会社に就職するのですが、この会社がとても給料が高いです。ですので、公認会計士の年収水準はとても高いです。
ですので、公認会計士試験受験生は論文式試験の合格を一旦のゴールと考えています。
なお、公認会計士試験向けの予備校は論文式試験合格までのコースを開講しています(予備校は終了考査対策のカリキュラムも用意していますが、この記事で紹介しているのは論文式試験合格までのコースです)。
公認会計士予備校比較①予備校ってどんなところ?

先に結論
入学時期は、時期ごとのコースが用意されているのでいつでもOK。
一から勉強を始める1.5~2年ほどのコースに入学するのが一般的。
公認会計士予備校の費用を紹介する前に、まずは予備校がどんなところかを説明します。
概要
公認会計士の予備校は会計について全くの初心者の状態から、1.5~2年ほどで公認会計士試験への合格を目指す予備校です。
入学したらテキスト、問題集や答練という模擬試験のようなものが配布され、それらを使って勉強を進めていきます。
入学費用にはそれらの教材費も含まれています。
入学時期・期間
公認会計士の予備校には「春コース」とか「秋冬コース」など色々なコースがあるのですが、その時期ごとにコースを用意しているので、いつでも入学できます。
期間は短いもので1.5年、長いもので2.5年ほどで、だいたいの人が1.5~2年のコースに入ります。合格は2~3年で目指すのが一般的です。
また、すでに公認会計士の勉強を進めている人向けのコースもあります。そういうコースでは1年ほどのコースもあります。
通学と通信
公認会計士の予備校は、どこも通学と通信2つのコースを用意しています。
通学の場合、実際に校舎に通って教室で授業を受けます。また、多くの予備校には自習室があるので、授業以外の時間はそこで自習することも可能です。
通信の場合、教材が自宅に送られてきて、講義はwebなどで見る、という感じです。
それぞれのメリットは以下です。
・講師に直接質問できる。
・周りに切磋琢磨できる仲間がいる。
「通学」のデメリット
・仲間とだらけてしまう人もいる。
・通学の時間がかかる。
・通学時間がかからない。
・自分のペースで勉強を進められる。
「通信」のデメリット
・勉強仲間ができない。
・講師に直接は質問できない。(電話やメールでは質問できます。)
こんな感じです。
勉強仲間がいた方が頑張れる人は「通学」、勉強仲間は邪魔になってしまう人・社会人で通学時間がもったいない人は「通信」が良いと思います。
公認会計士予備校の費用②各予備校の費用まとめ

先に結論
2年のコースで、受講料は大手三校(CPA会計学院、TAC、大原)は75~80万円ほど、中堅2校(LEC、クレアール)は55万円ほど。
毎年、合格者全体の8~9割が毎年大手3校で独占されている。
各予備校の料金を比較
CPA会計学院、TAC、大原、LEC、クレアールのメジャー予備校5校の、初学者対象の2年間・1年間のコースの費用を紹介。
| 予備校とコース名 | 実施期間 | 対象となる試験 | 料金 |
| CPA会計学院 | |||
| 2年スタンダードコース | 約2年4か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 780,000円 |
| 1.8年スタンダードコース | 約2年0か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 760,000円 |
| TAC | |||
| 2年チャレンジ本科生 | 約2年2ヵ月 | 短答式2回、論文式2回に対応 | 810,000円 |
| 短期集中本科生 | 約1年2ヵ月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 730,000円 |
| 大原 | |||
| 2年初学者合格コース | 約1年6か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 780,000円 |
| 1年初学者合格コース | 約1年3か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 740,000円 |
| LEC | |||
| 短答・論文合格コース | 約9か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 428,000円 |
| クレアール | |||
| 2.5年トータルセーフティコース | 約2年6か月 | 短答式4回、論文式2回に対応 | 650,000円 |
※各校、季節ごとに料金が微妙に違うので、おおよその額。
料金は大手3校と中堅2校の2グループに分かれる
表を見てお分かりかと思いますが、公認会計士予備校は
2年コースで80万円前後の大手予備校 CPA会計学院、TAC、大原
費用の安い中堅予備校 LEC,クレアール
という2つのグループに分かれます。
こういわれると安いほうに行きたくなるかもしれませんが、私は大手予備校がおすすめです。
その理由は
①大手3校合計で毎年、公認会計士試験合格者の8~9割にあたる1000~1200人ほど合格者を輩出しており、費用は高いですがそのカリキュラムや教材の質が圧倒的に高いから
②もし試験に落ちたら、もう1年通う可能性もある。そう考えると、合格可能性の高まる大手の方がトータルで考えると安いから
それに、75~80万円ほどの費用には教材費や試験合格後の就活相談費用など全てが含まれており、決して高くない値段設定です。
おすすめはCPA会計学院
そして、筆者が最もおすすめする予備校はCPA会計学院です。
その理由は
①合格者数が圧倒的に多いから(2024年の合格者数:973名(全予備校でトップ) 合格者占有率60.7%)
②サポートが充実しているから
また、CPA会計学院は資料請求すると、割引券や割引の案内が付いてくることがあるので、上記の金額からさらに安くなります。
おすすめの理由はこの記事の5章で詳細に解説しています。
また、費用面以外の比較は以下の記事にまとめてますので、よかったら参考にしてください。
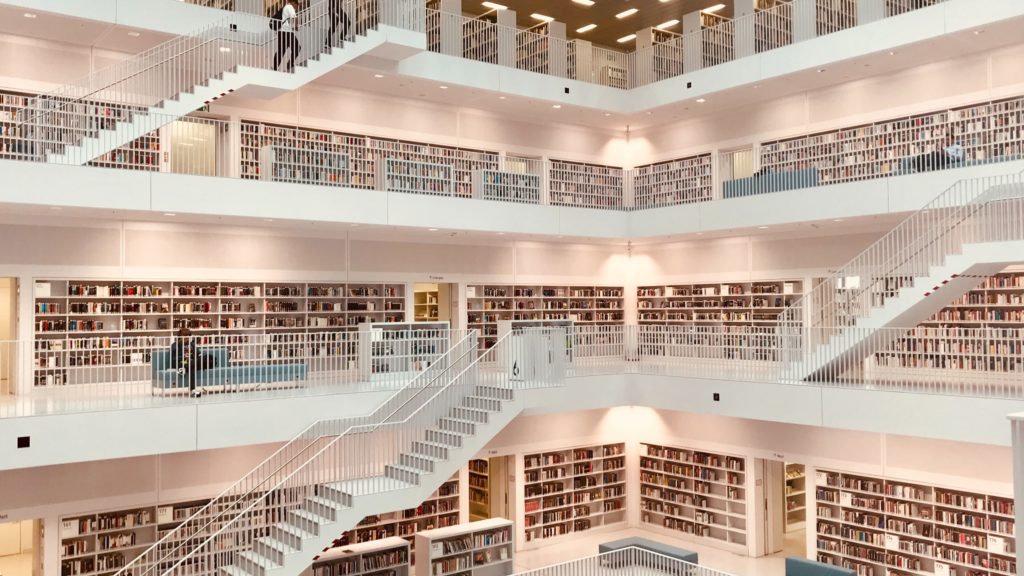
公認会計士試験用の予備校を検討している人向け。内容⇒CPA会計学院,TAC、大原、LEC、クレアールという5つの予備校をあらゆる面で比較しています。
各予備校の費用詳細
CPA会計学院
|
コース名 |
実施期間 |
対象となる試験 |
通学 |
通信 |
通学・通信併用 |
| 初学者向けコース | |||||
| 2年スタンダードコース | 約2年4か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 780,000円 | 750,000円 | 810,000円 |
| 2年速習コース | 約2年4か月 | 短答式3回、論文式2回に対応 | 800,000円 | 770,000円 | 830,000円 |
| 2年超速習コース | 約2年4か月 | 短答式4回、論文式2回に対応 | 820,000円 | 790,000円 | 850,000円 |
| 1.8年スタンダードコース | 約2年0か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 760,000円 | 720,000円 | 790,000円 |
| 1.8年速習コース | 約2年0か月 | 短答式3回、論文式2回に対応 | 780,000円 | 740,000円 | 810,000円 |
| 1年スタンダードコース | 約1年4か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 700,000円 | 660,000円 | 730,000円 |
| 受験経験者向けコース | |||||
| 上級総合Wチャンスコース | 約1年3か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 480,000円 | 480,000円 | 510,000円 |
| 会計大学院修了者Wチャンスコース | 約1年3か月 | 短答式2回(企業法のみ)、論文式1回に対応 | 446,000円 | 446,000円 | 476,000円 |
| 上級総合ストレートコース | 約1年3か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 470,000円 | 470,000円 | 500,000円 |
| 会計大学院修了者ストレートコース | 約1年3か月 | 短答式1回(企業法のみ)、論文式1回に対応 | 436,000円 | 436,000円 | 466,000円 |
| 上級論文マスターコース | 約1年3か月 | 論文式1回に対応 | 350,000円 | 350,000円 | 380,000円 |
| 上級論文答練コース | 約1年3か月 | 論文式1回に対応 | 290,000円 | 290,000円 | 320,000円 |
| 12月短答受験コース | 約6か月 | 短答式1回に対応 | 320,000円 | 320,000円 | 350,000円 |
| 5月短答受験コース | 約11か月 | 短答式1回に対応 | 320,000円 | 320,000円 | 350,000円 |
| 8月論文受験コース | 約3~8か月 | 論文式1回に対応 | 224,000円 | 224,000円 | 254,000円 |
TAC
| コース名 | 実施期間 | 対象となる試験 | 教室(ビデオブース)+Web講座 | Web通信 | DVD+Web通信 |
| 初学者向けコース | |||||
| 短期集中本科生 | 約1年2ヵ月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 730,000円 | 730,000円 | 810,000円 |
| 2年チャレンジ本科生 | 約2年2ヵ月 | 短答式2回、論文式2回に対応 | 810,000円 | 810,000円 | 890,000円 |
| 2年L本科生 | 約2年2ヵ月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 760,000円 | 760,000円 | 840,000円 |
| 2年S本科生 | 約2年 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 780,000円 | 780,000円 | 860,000円 |
| 高校生向け本科生 | 約2年2ヵ月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 610,000円 | 610,000円 | 690,000円 |
| 受験経験者向けコース | |||||
| 上級Wチャンス本科生 | 約1年1ヵ月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 441,000円 | 441,000円 | 497,000円 |
| 基礎フルパック上級本科生 | 約1年1ヵ月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 600,000円 | 600,000円 | 660,000円 |
| 上級ストレート本科生 | 約1年 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 413,000円 | 413,000円 | 469,000円 |
| 論文専攻上級本科生 | 約9月 | 論文式1回に対応 | 378,000円 | 378,000円 | 434,000円 |
| 上級論文答練パック本科生 | 約9月 | 論文式1回に対応 | 301,000円 | 301,000円 | 357,000円 |
大原
| コース名 | 実施期間 | 対象となる試験 | 教室通学 | 映像通学 | Web通信 | DVD通信 |
| 初学者向けコース | ||||||
| 1年初学者合格コース | 約1年3か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 無し | 740,000円 | 720,000円 | 810,000円 |
| 1年初学者合格コース [前期] | 約7か月 | 短答式1回に対応 | 無し | 416,000円 | 無し | 無し |
| 2年初学者合格コース | 約1年6か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 780,000円 | 780,000円 | 760,000円 | 850,000円 |
| 2年初学者合格コース [前期] | 約9か月 | 短答式1回に対応 | 436,000円 | 436,000円 | 472,000円 | 426,000円 |
| 1.5年オータム初学者合格コース | 約1年6か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 770,000円 | 770,000円 | 770,000円 | 840,000円 |
| 1.5年ウィンター初学者合格コース | 約1年6か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 760,000円 | 760,000円 | 740,000円 | 830,000円 |
| 短答集中パック | 約1年3か月 | 短答式1回に対応 | 330,000円 | 330,000円 | 320,000円 | 350,000円 |
| 受験経験者向けコース | ||||||
| 上級フルパック合格コース | 約1年6か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 507,000円 | 507,000円 | 497,000円 | 517,000円 |
| 上級ベーシック合格コース | 約1年2か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 810,000円 |
| 上級短答論文合格コース(5月短答) | 約1年 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 425,000円 | 425,000円 | 415,000円 | 436,000円 |
| 12月短答必勝履修者のための上級論文対策合格コース | 約9か月 | 論文式1回に対応 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | 368,000円 |
| 上級論文総合合格コース | 約1年 | 論文式1回に対応 | 399,000円 | 399,000円 | 389,000円 | 408,000円 |
| 上級論文対策合格コース[短答免除者対象] | 約9か月 | 論文式1回に対応 | 360,000円 | 360,000円 | 350,000円 | 379,000円 |
| 上級論文演習合格コース[短答免除者対象] | 約9か月 | 論文式1回に対応 | 273,000円 | 273,000円 | 263,000円 | 285,000円 |
LEC
| コース名 | 実施期間 | 対象となる試験 | 通学 | Web通信 | DVD通信 |
| 初学者向けコース | |||||
| 短答合格コース | 約1年4か月 | 短答式2回に対応 | 298,000円 | 278,000円 | 378,000円 |
| 学習経験者向けコース | |||||
| 論文式試験対策コース | 約1年10か月 | 論文式1回に対応 | 288,000円 | 268,000円 | 358,000円 |
| 短答・論文合格コース | 約9か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 428,000円 | 398,000円 | 468,000円 |
| 圧縮短答・論文合格コース | 約9か月 | 短答式1回、論文式1回に対応 | 368,000円 | 338,000円 | 398,000円 |
| 短答合格パック | 約5か月 | 短答式1回に対応 | 218,000円 | 198,000円 | 268,000円 |
| 圧縮短答合格パック | 約5か月 | 短答式1回に対応 | 178,000円 | 158,000円 | 208,000円 |
クレアール
| コース名 | 実施期間 | 対象となる試験 | web通信 |
| 初学者向けコース | |||
| 1.5年合格全力投球コース | 約1年6か月 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 520,000円 |
| 2.5年トータルセーフティコース | 約2年6か月 | 短答式4回、論文式2回に対応 | 650,000円 |
| 3.5年トータルセーフティコース | 約3年6か月 | 短答式6回、論文式3回に対応 | 770,000円 |
| 4.5年トータルセーフティコース | 約4年6か月 | 短答式6回、論文式3回に対応 | 800,000円 |
| 2年スタンダード短答合格コース | 約2年 | 短答式2回に対応 | 300,000円 |
| ストレート春短答合格コース | 約1年6か月 | 短答式2回に対応 | 310,000円 |
| 2年スタンダード合格コース | 約2年 | 短答式2回、論文式1回に対応 | 540,000円 |
| ハイスピード型短答・論文トータルサクセスコース | 約2年6か月 | 短答式3回、論文式2回に対応 | 540,000円 |
| 受験経験者向けコース | |||
| 論文合格目標 上級論文合格コース | 約10か月 | 論文式1回に対応 | 285,000円 |
| 上級1.5年論文トータルセーフティコース | 約1年6か月 | 論文式2回に対応 | 300,000円 |
※クレアールは通学コースはない。通信のみ。
公認会計士予備校の費用③安くする方法
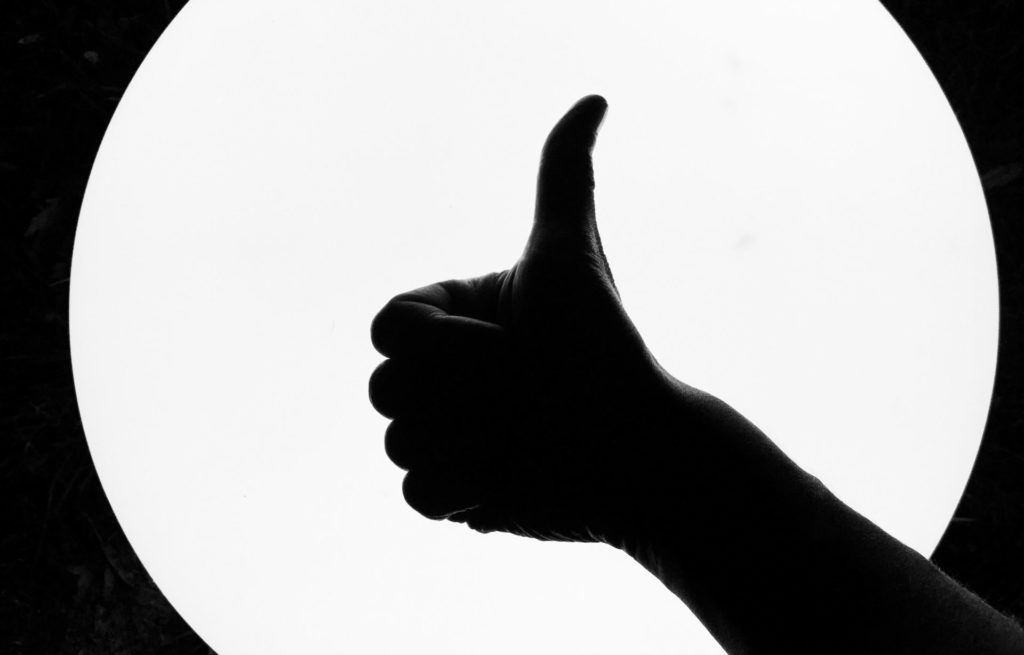
ここからは費用を安くする方法を紹介します。
教育訓練給付制度
これはハローワークによる制度で、受講費用の20%(最大10万円)がハローワークから支給される制度です。
会計士講座はどこも50万を超えているので、満額受け取れます。
ただし、給付にはもちろん条件があり、その条件とは以下になります。
初めてこの制度を利用する方・・・雇用保険加入期間が通算1年以上
以前にこの制度を利用したことがある方・・・前回利用開始日から雇用保険加入期間が通算3年以上
このように雇用保険の加入期間が条件となっていますので、
1年以上社会人の経験がある方はほぼ間違いなく条件を満たしていると思います。
また、アルバイトでも勤務時間によっては雇用保険に加入しているはずなので、学生の方も条件を満たしている可能性があります。
ただ以下の3校はHP内で案内も出しているのですが、他の2校は案内が出ていないのでこの制度は受けられないかと思われます。(この給付を受けるには、予備校側が厚生労働大臣指定の一般教育訓練として認められる必要があります。)
奨学金制度・特待生制度
公認会計士予備校の中には、成績優秀者は割引料金で受講できる奨学生制度を用意しているところもあります。
受講料を最大8割割引してくれる制度や、お金を貸してくれる制度など様々ですので、確認してみてください。
CPA会計学院の資料請求をする
CPA会計学院に資料請求すると、割引や無料講座がついてくることがあります(時期による)。無料で入門講座を受けられるので、公認会計士の予備校の雰囲気もつかめておすすめです。
予備校選びに迷っているなら、比較材料にもなるので、まずは資料請求するのがおすすめです。
公認会計士予備校の費用④おすすめの予備校

先に結論
おすすめの予備校はCPA会計学院。理由は①合格者数が圧倒的に多いから②講師への質問が最もしやすいから。
費用を押さえたいならクレアールもあり。
CPA会計学院へのリンクは以下

ここでは、おすすめの予備校をご説明いたします。
私が予備校を評価するうえで重要視している点は以下です。
・教材はわかりやすいか
・授業はわかりやすいか
・質問に対するフォロー体制
・デジタル対応
教材・授業のわかりやすさは当然ですが、こちらからの質問にしっかり答えてくれるかというのは、とても重要な点の一つだと思います。質問しても疑問が解決しなかったり、なかなか質問できない環境だと勉強の効率が落ちるので。
また、予備校に入っても学習の中心は自習になりますので、自習のしやすさ(いつでもどこでも学習できるか)と言う意味で、デジタル対応も重要な点の一つです。教材や授業がネットで見れたり、ネットから質問ができると勉強の効率が上がります。
これらの点から、私がおすすめする予備校はCPA会計学院です。正直、今入学するならこの予備校一択です。また、コスパ面を重視するならLECです。
CPA会計学院

| 受講料 | 60~85万 |
| 直近の合格者数 | 973名 |
| 校舎の数 | 5校 |
CPA会計学院のメリットは以下です。
驚異的な合格者数
教材・講師の質の高さ
デジタル対応が最も進んでいる予備校
フォロー体制も予備校の中で最も充実している
驚異的な合格者数
CPA会計学院は2024年の合格者数トップの公認会計士予備校です(2024年 合格者数973名 合格者占有率60.7%)。
公認会計士試験の予備校は、TACと大原が昔からの大手で、2015年ほどまではこの2校で合格者の大半を独占していました。
そこに近年急成長したのがCPA会計学院で、2021年に合格者数でトップに立ち、今では合格者占有率60.7%と合格者の6割を占めています。
これだけ急成長した理由としては、講師の質の高さ、教材の質の高さ、サポート体制の充実が挙げられます。詳細を以下で解説していきます。
有名講師陣
CPA会計学院は数年前に他の予備校から有名講師を引き抜いており、講師の方はみなさん公認会計士会では有名な講師です。ですので、授業の質はとても高いです。
また、CPA会計学院にはチューターという制度があるのですが、こちらもとても評判がいいです。チューターとは前年に公認会計士試験に合格した方達のことで、大学在学中に合格した方が中心のようです。
CPA会計学院の校舎には講師だけでなく、このチューターが常駐しており、生徒の質問対応をしています。前年に実際に合格しているチューターの方々は知識が新鮮ですし、自分が抱えているのと同じような悩みを必ず経験しているはずなので、そんなチューターの方々に質問できるのは、とても有意義だと思います。
教材の質の高さ
CPA会計学院の教材はとても質が高いことで有名です。私も実際にCPA会計学院の教材を使ったのですが、とても良い教材でした。教材が分かりやすく書いてあることは当然として、私が非常に助かったのが、CPA会計学院の教材には、範囲ごとにA~Cの重要性が書いてあることです。
公認会計士試験の範囲の中には、ほとんど本番で出題されないので捨てるべき部分としょっちゅう出るので重点的に勉強すべき部分があります。A~Cの重要性はその判断に使え、それは学習の効率をグンと上げてくれます。
また、この重要性は答練や模試にも書いてあるので、実際の試験で「難しいので捨てるべき問題を捨てる練習」にも使えます。公認会計士試験では「難易度が高すぎて、解こうとするととても時間がかかるし正答率も低いので捨てるべき問題」が毎年必ず出題されます。
問題を解く練習も大切ですが、問題を捨てる練習も同じくらい大切です。その練習ができるのはとても助かります。
デジタル対応
CPA会計学院は大手予備校の中で最もデジタル対応が進んでいます。具体的には以下のようなデジタル化が図られています。
・全ての教材がwebでも読める。(もちろん紙媒体の物ももらえます)
・講義は全てwebでも受講できる
・講義は音声データ版もある(電車や寝るときにイヤホンで講義を聴ける)
ここまでデジタル化されていますので、いつでもどこでも勉強できます。勉強は電車やカフェでも勉強したいという方にとって、これはとても助かると思います。
通信のフォロー体制
CPA会計学院の強みとして校舎に講師が常駐しているので、いつでも質問できると記載いたしましたが、CPA会計学院は通信コースの方も講師・チューターに質問できます。
その方法は電話・メール・Zoom・バーチャル校・対面と全ての質問方法がそろっていますので、通信でもわからないところはすぐに質問できます。
また、授業は上記のweb講義を視聴でき、教材は紙の物とデジタル教材の両方をもらえますので、通信と通学の差はほとんどないと思います。
まとめ
これら以外にも、CPA会計学院は公認会計士専門の予備校である、綺麗な自習室がある、女子専用自習ブースがあるなど環境が整いまくってます。
正直、本気で合格を目指すならCPA会計学院に入っておけば間違いないです。
予備校選びに迷っているなら、比較材料にもなるので、まずは資料請求するのがおすすめです。
クレアール

| 受講料 | 45~60万 |
| 直近の合格者数 | 非公開 |
| 校舎の数 | 通信のみ |
クレアールのメリットは以下です。
受講料が安い
効率的カリキュラム
デジタル対応が充実している
いつでも回数無制限で電話で講師に質問できる
受講料が安い
クレアールのメリットは何といっても受講料の安さです。大手3校(CPA会計学院、大原、TAC)の受講料が、コースにもよりますがだいたい75~85万円ほどであるところ、クレアールは45~60万円ほど、短答式までのコースなら300,000円となっております。
「安いんなら、その分質も落ちるんじゃないの?」
このように思う方もいらっしゃると思いますが、それほど他の予備校と変わりません。私は全ての予備校のテキストを読んで比較したのですが、テキストも他と大して変わりません。また、以下に記載しているようなクレアールならではの強みもたくさんあります。
効率的カリキュラム
クレアールは非常識合格法という他の予備校とは異なる独自のカリキュラムをとっています。
その内容は、短答式の内から論文式の勉強も始める、よく出る範囲を重点的に勉強するというもので、短期合格を目指すもののようです。
公認会計士試験の特徴はとにかく範囲が広いことです。
ただ、その試験範囲の中にはほとんど試験では出題されない範囲もあります。
そのため、公認会計士試験の攻略法は試験に出る範囲を重点的に学習し、ほとんど出ない範囲はある程度捨てるという方法です。合格した人はこういった勉強法を取っており、実際、私もそういった勉強法で合格しました。
その点、クレアールの教材は最初から、試験によく出る範囲を重点的に、ほとんど出ない範囲はカットされた教材となっております。
そのためクレアールの教材を使えば自ずと公認会計士試験向けの勉強法となり、合格への最短ルートを進めると思います。
デジタル対応
クレアールは講義・教材共にPC・スマホ・タブレットすべての端末から閲覧・ダウンロード可能であり、完全にデジタル対応しています。
またそれだけでなく、クレアールは2025年合格目標コースからCROSS STUDYという独自の学習支援ツールをリリースしています。
これはオンラインで問題集が解けるシステムであり、自分だけの問題集のカスタマイズ、定期的な確認問題の配信などの機能が盛り込まれたオンライン学習ツールです。
「自分が苦手な範囲だけをまとめたオリジナル問題集をカスタマイズ」「配信される確認問題を解くことで知識の掘り起こし」など使い方は自由自在です。
これは範囲がとても広く、効率的に学習を進めることが重要な公認会計士試験にとてもマッチしたシステムであり、筆者としてはとてもおすすめできるシステムです。
フォロー体制
クレアールでは電話・メール・SNSで講師に質問可能で、電話は回数無制限です。
他の予備校では講師への質問は予約制であったり、1か月ごとの回数制限があったりするのですが、クレアールにそういったものはないのでとても質問しやすい環境だと思います。
まとめ
ここまで書いたように、クレアールはとても安いですが、とても魅力のある予備校です。
そのためコスパを重視する方にはクレアールがおすすめです。
クレアールのことをもっと知りたい方は資料請求するのが手っ取り早いです。クレアールへの資料請求は以下です。
公認会計士予備校の費用⑤まとめ

この記事に書いたことをまとめると以下です。
まとめ
予備校の受講料は最も一般的な大手予備校のコースで70~85万円ほど。
毎年、合格者全体の8~9割が大手予備校の受講生で独占されている。
おすすめの予備校はCPA会計学院。理由は①合格者数が圧倒的に多いから②サポートが充実しているから
CPA会計学院へのリンクは以下
予備校については以下で全て比較していますので、よかったら参考にしてください。
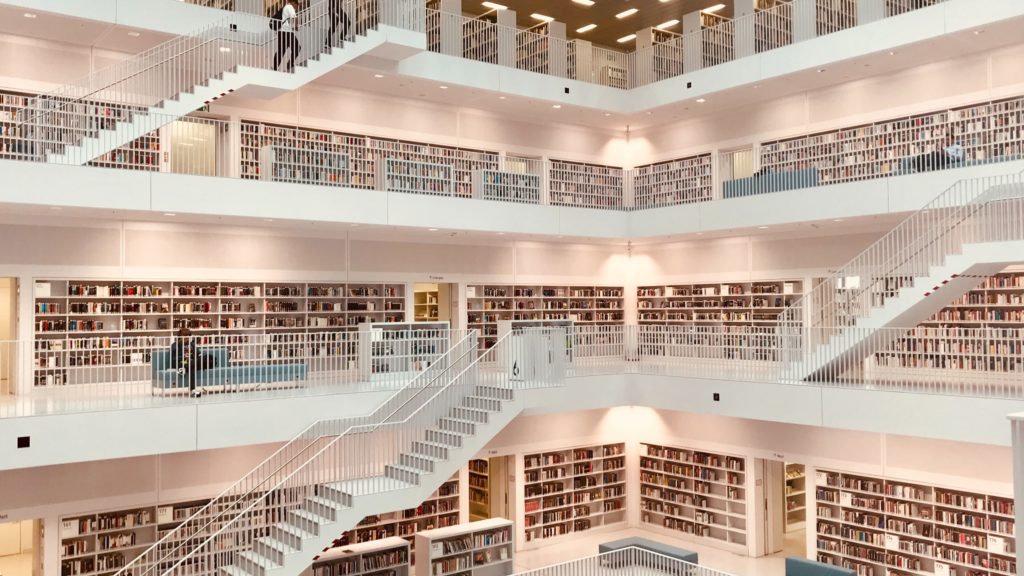
公認会計士試験用の予備校を検討している人向け。内容⇒CPA会計学院,TAC、大原、LEC、クレアールという5つの予備校をあらゆる面で比較しています。