

公認会計士試験を目指すか悩んでいる大学生「公認会計士を目指そうかと思うが、公認会計士試験に合格するにはどれくらいの勉強時間が必要なんだろう?そもそも大学に通いながら公認会計士試験には合格できるんだろうか?」
この記事ではこういった疑問に答えます。
こんな人向けの記事です
公認会計士を目指そうか悩んでいる大学生
公認会計士試験合格に必要な勉強時間を知りたい人
この記事の信頼性
この記事の筆者は、2年の勉強期間で公認会計士試験に合格しています。
目次
大学生が公認会計士になる勉強時間①公認会計士試験とは?

公認会計士試験の仕組み
公認会計士試験に合格するための勉強時間を解説する前に、まずはそもそもの公認会計士試験制度を説明していきます。
公認会計士になるまでの流れをざっくり説明すると以下のようになります。
①短答式試験(1次試験)
②論文式試験(2次試験)
③会計に関する職業に就職(8~9割の人が監査法人に就職)
④2年間の実務経験&3年間補修所の講習を受ける
⑤終了考査(3次試験)
⑥終了考査に合格し、晴れて公認会計士として認定される。
こんな感じです。
最後の終了考査に合格してやっと公認会計士として認められるのですが、
終了考査を受けるためには「2年以上の会計に関する業務経験」が要件となっています。
ですので、論文式試験合格後に、会計に関する職業に就職する必要があり、
これが8~9割の人が監査法人という法人に就職するのですが、
この監査法人がとても給料が良いです。
また、終了考査は受験者の5~7割が合格する、つまりほとんどが合格できる試験です。
ですので、論文式試験(2次試験)に合格するまでを一旦のゴールと考えていただいて問題ありません。
一般的にも公認会計士試験の受験というと、この論文式試験までを言います。
ですので、この記事でも論文式試験合格までの勉強時間について解説していこうと思います。
大学生で公認会計士を目指す方法(予備校か独学か)
公認会計士試験を目指す方法は予備校に入るのと独学の2つの方法があります。
私は独学で合格したのですが、一般的には9割以上の方が予備校に入ります。
予備校は、大学に行きながら通えるものなの?
こういった疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
予備校も大学のようにカリキュラムがあり、そのコースによって異なるのですが、やはり通学コースの方は集3日以上は通うことになります。
ですので、もちろん大学の授業後に通うことができますが、大学の授業に余裕の出る大学3年生(文系)から目指す方が多いようです。
大学が忙しい型や通のは面倒という方は、予備校には通信コースもあるのでそちらがおすすめです。
通信だからと言って通学と比べると不利というようなことは全くなく、授業もWEBやDVDにて視聴できます。
公認会計士予備校は大きい所でいうと5つあります。
その比較は以下の記事にまとめてますので、よかったら参考にしてください。
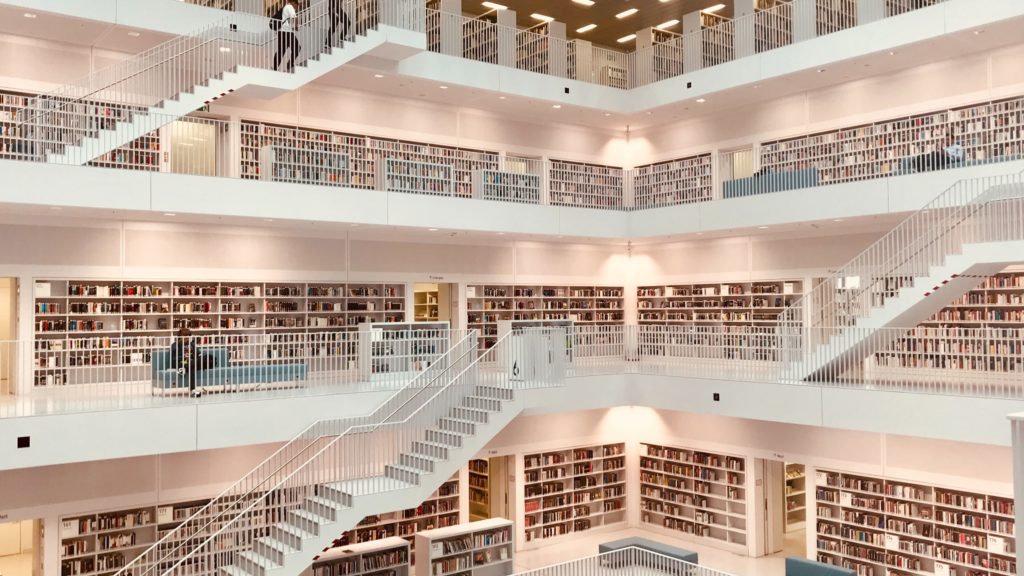
公認会計士試験用の予備校を検討している人向け。内容⇒CPA会計学院,TAC、大原、LEC、クレアールという5つの予備校をあらゆる面で比較しています。
もちろん、独学合格も不可能ということは全くありません。
むしろ、自分で勉強のスケジュールを立てられる方なら独学の方がいいと私は思っています。
つまり
しっかりと授業を受けて予備校のカリキュラムで勉強を進めたい人→予備校
自分で勉強計画を立てて自分のやり方で勉強を進めたい人→独学
予備校か独学かは上のように決めればいいと思います。
大学生が公認会計士になる勉強時間②合格までの勉強時間

ここから本題に入ります。
合格までの勉強時間
合格までの勉強時間ですが、ズバリ3000~5000時間です!
具体的なイメージは以下のような感じです。
例)大学を卒業して勉強に専念するタイプ
(仕事や学校はないので、毎日8.5時間勉強する。)
一日8.5時間 × 365日 = 3102.5時間(1年間の勉強時間)
⇒1~1.5年で合格が狙える。
例)仕事や大学に通いながら勉強するタイプ
(平日は仕事・大学の後なので3時間、休日は8時間勉強する)
(平日3時間 × 5日) + (休日8時間 × 2日) =31時間(1週間の勉強時間)
31時間 × 52週間 =1612時間(1年間の勉強時間)
⇒2~3年で合格が狙える。
こんな感じです。
また、科目ごとの勉強時間の目安は以下です。
(3000時間での合格の場合)
短答式
財務会計論 600時間
管理会計論 300時間
監査論 200時間
企業法 400時間
論文式
財務会計論 300時間
管理会計論 200時間
監査論 200時間
企業法 200時間
租税法 400時間
選択科目 200時間
大学で簿記を勉強している場合の勉強時間
商学部の方なら、大学の授業で簿記をすでに勉強済みという方も多いと思います。
大学で簿記を勉強している場合の合格までの勉強時間ですが、日商簿記の合格までの勉強時間は以下のように言われています。
簿記3級 50時間
簿記2級 200時間
簿記1級 400時間
公認会計士試験の範囲は、簿記1~3級までの範囲を含んでいます。
ですので、簿記の資格を持っている方は、上記の簿記の勉強時間を控除した勉強時間で考えていいと思います。
つまり、簿記2級を持っている方なら公認会計士試験合格までの勉強時間は2800~4800時間、簿記1級を持っている方なら公認会計士試験合格までの勉強時間は2600~4600時間、というように考えていいと思います。
実際、簿記1級まで理解できていれば、公認会計士試験の短答式の財務会計論と管理会計論を6割程度理解できると思います。
ですので、上記の勉強時間の考え方は妥当だと思います。
大学院で科目免除
公認会計士試験の短答式では、以下の要件を満たす方は財務会計論、管理会計論、監査論の3科目が免除となります。
会計専門職大学院において、
(a)簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
(b)原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
(c)監査論その他の監査に属する科目に関する研究
により、上記(a)に規定する科目を10単位以上、(b)及び(c)に規定する科目をそれぞれ6単位以上履修し、かつ、上記(a)から(c)の各号に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者
短答式4科目中3科目が免除になるのでかなり大きいですよね。会計専門職大学院を卒業されてる方・卒業予定の方は、上記の科目別勉強時間より、ゼロの状態から勉強を始める方と比べて、約1100時間ほど短い勉強時間で合格を狙えると思います。
大学生が公認会計士になる勉強時間③公認会計士試験の科目別勉強時間

先に結論
会計学は計算と理論を並行して進めると効率が良い。
理論問題はとにかく問題集を繰り返し解くのがおすすめ。
選択科目は、比較的勉強時間が少ない経営学か統計学がおすすめ。
公認会計士試験の科目別勉強時間①財務会計論
短答式
財務会計論の短答式の勉強時間は600時間です。これは簿記2級までの勉強時間が200時間、残りの400時間が財務会計論の勉強というイメージです。
財務会計論は計算と理論があり、どちらもとにかく範囲が広いです。ですので膨大な勉強時間がかかります。
そんな財務会計論の勉強時間をできるだけ短くするおすすめの勉強法は「計算と理論を並行して進める」ということです。
財務会計論の計算問題は理論を理解していないと解けません。また理論問題は計算問題で会計処理のイメージをつかんでいた方が理解しやすいです。ですので、計算と理論、どちらかを先に進めていくより、ずっと並行して同じペースで進めるのが効率が良いんです。
おそらく勉強を始めると、最初は計算の方がとっつきやすく、理論はわかりにくいので、計算をどんどん進めたくなると思うのですが、そこはぐっと我慢して理論も同じペースで進めてください。
そうすると、計算問題を勉強しているから理論問題はイメージしやすくなり、また、計算でなんとなくつかめたイメージが、理論でしっかりと裏付けされた知識になっていく、という効率的な勉強が進められます。
論文式
財務会計論の論文式の勉強時間は200時間です。
財務会計論の論文式は、短答式と同様に計算と理論があります。計算は記述式になりますが、連結や結合会計の複雑な問題も出題されるようになるだけで、短答式から出題範囲は大きく変わりませんので、計算の勉強は短答式の勉強の延長で問題ありません。
理論は、短答式の問題とは中身が変わります。短答式では、財務会計の基準や概念の知識を問われるような問題が出題されますが、論文式ではその基準や概念の裏にある考え方・理論が出題されます。問題の内容が変わるので、理論問題は論文式のための対策に勉強時間をかける必要があります。
ですので、財務会計論の論文式のおすすめの勉強法としては、計算は最初から模試や答練などの本番レベルの問題を解いて大丈夫です。短答式に合格した方なら普通に解けると思います。連結や結合は短答式より難しくなっていると思うので、そういった問題はテキストで調べて理解していきましょう。
理論は短答式とは中身が異なりますが、短答式で基礎が身についていれば、論文式の問題も理解していけると思います。とにかくひたすら理論問題集や模試・答練を解いて財務会計の考え方を頭に入れていきましょう。
本番では出題される問題のパターンが決まっています。理論問題集や模試・答練に出た問題と同じ問題が、必ず本番でも出題されますので、問題集等の問題をそのまま覚えていければ本番でも結果は出ます。
詳細な勉強法は以下の記事にまとめましたのでよかったら参考にしてください。
公認会計士試験の科目別勉強時間②管理会計論
短答式
管理会計論の短答式の勉強時間は300時間です。管理会計論も財務会計論と同様に簿記2級までの勉強時間を含めています。簿記が100時間、管理会計論が200時間というイメージです。
管理会計論の短答式は計算問題と理論問題が出題されます。
計算問題は原価計算を中心とした問題で、理論問題は原価計算基準と言う基準書を中心とした問題が出題されます。
そんな管理会計論のおすすめの勉強法は、原価管理基準を覚えることです。管理会計論の理論問題はだいたい6~8問出題されるのですが、そのうち3~5問が毎年原価管理基準から出題されます。ですので、原価管理基準を覚えるだけで30~40点取れるんです。
原価管理基準は30ページほどでそれほどボリュームがなく、また、よく出題されるところも決まっていますので、覚えるのにそれほど苦労はしないと思います。また、原価管理基準は原価計算の方法について記載した基準であり、計算問題は原価計算が中心ですので、原価管理基準を覚えれば計算問題も点が取りやすくなります。
論文式
管理会計論の論文式の勉強時間は200時間です。
管理会計論の論文式は、財務会計論と同じように、計算問題は、回答形式が記述式になるだけで、問題の内容は短答式と変わりません。理論問題は短答式で覚えた知識の裏にある考え方・理論が出題されます。
ですので、おすすめの勉強法としては、計算は模試・答練解くことです。中身は変わりませんので、短答式に合格した方なら最初から解けると思います。
理論問題は、理論問題集や模試・答練を繰り返し解くということです。
はっきり言って、管理会計論の論文式に、これ以上の工夫した勉強法等はありません。短答式から理論問題が変わるだけですので、計算は短答式で付けた基礎をより鍛えること、理論は問題をひたすら繰り返す、これをやっていれば合格点取れると思います。
詳細な勉強法は以下の記事にまとめましたのでよかったら参考にしてください。
公認会計士試験の科目別勉強時間③監査論
短答式
監査論の短答式の勉強時間は200時間です。
監査論の短答式は理論問題のみが出題されます。監査論は短答式の科目の中では比較的ボリュームが少ない科目です。
ですので、おすすめの勉強法は、理論問題集や模試・答練を繰り返し解く、それだけです。これらを繰り返し解いて、わからないところをテキストや監査基準委員会報告書等で調べる、それだけで合格点取れると思います。
比較的ボリュームの少ない科目ですので、効率的に勉強して、他の科目に勉強時間をかけられるようにするべきです。
論文式
監査論の論文式の勉強時間は200時間です。
監査論は論文式科目の中でもボリュームの少ない科目④す。内容としては、短答式では監査についての基準等の知識を問われる問題が多いですが、論文式は、監査の考え方についての記述式問題が主です。
ただ、その勉強のためには、短答式で監査の基本を理解していることがとても重要であり、短答式で監査の基本を理解できている人であれば、それほど苦戦しないと思います。
おすすめの勉強法としては、やはり模試・答練を繰り返しとく、と言うことしかないと思います。監査の考え方についての記述式の問題ですので、実際に問題を解いて、監査の考え方を理解していく、また、論文の書き方に慣れていくということが、最も重要だと思います。
詳細な勉強法は以下の記事にまとめましたのでよかったら参考にしてください。
公認会計士試験の科目別勉強時間④企業法
短答式
企業法の短答式の勉強時間は400時間です。
企業法の短答式は、会社法、金融商品取引法、商法の一部についての理論問題が出題されます。企業法はとても範囲が広く、短答式科目の中でもボリュームの大きい科目です。
その勉強法としては、とにかく知識を頭に入れていかないといけないので、やはり、理論問題集や模試・答練を繰り返し解き、わからないところをテキストで調べるのが良いと思います。
ここで注意すべきなのが、決してノートにテキストの内容をまとめたりはしない方がいいです。私はテキストを1からノートにまとめたのですが、それだけで2か月かかってしまい、とても時間を無駄にしてしまいました。テキストはあくまで、問題を解いてわからなかった時に調べるために使い、まとめた時はテキストに直接書き込むのが良いと思います。
論文式
企業法の論文式の勉強時間は300時間です。
企業法は論文式でも勉強量が多い科目です。その理由は、企業法の論文式は、問題の内容が短答式とはかなり異なるからです。
企業法は、短答式では会社法、金融商品取引法、商法の一部についての知識を問われるような問題ですが、論文式では、実際のその法律の効力、適用、考え方などについての論文を記述する問題が出題されます。
これを解くためには当然短答式でしっかり会社法の基本を覚えることが必要ですが、短答式の延長では論文式は解けないので、やはり企業法の論文式はそれなりの勉強量が必要になります。
そんな企業法の論文式のおすすめの勉強法は、やはり問題集や模試・答練を繰り返し解くということです。論文を記述する問題ですので、やはり何度も実際に論文を書いて慣れていくしかありません。ただ、企業法の論文式では、出題される問題はある程度毎回決まっているので、問題集や模試・答練の問題の論点を覚えていければ、本番で得点は取れるようになっていきます。
ですので、やはり問題集や模試・答練を繰り返し解くというのが、最も効果的な勉強法になります。
詳細な勉強法は以下の記事にまとめましたのでよかったら参考にしてください。
公認会計士試験の科目別勉強時間⑤租税法
租税法の勉強時間は400時間です。
租税法はとにかく範囲が広く、また論文式から新たに追加される科目ですので、論文式の科目の中では最も勉強時間が必要になる科目です。
その内容は法人税法、所得税法、消費税法についての計算問題と理論問題です。
そんな租税法のおすすめの勉強法はやはり模試・答練を繰り返し解いていくということなのですが、租税法では、本番で問題を解くおすすめの順番があります。
その順番とは法人税法→所得税法→消費税法の順番です。なぜこの順番がおすすめなのかと言うと、税金の計算というのはいくつかのプロセスに分かれており、一つ一つのプロセスで計算をしていき、最終的に課税される税金の額が算出されるという形です。
このように税金の計算はプロセスごとに計算を行っていく形なので、最初の方のプロセスで計算を間違っていると、その後のプロセスの計算も誤りになることがあります。特にそういった特徴が強いのが消費税法で、最初の方で間違えると、全部不正解になるということもざらにあります。
ですので、消費税法はとてもリスクが高いんです。その反対に、法人税法は、一つのプロセスの計算ミスが他のプロセスの影響しにくいので、得点が取りやすいです。ですので、問題を解く順番としては、そのようなリスクが小さい順に法人税法→所得税法→消費税法の順となります。
まあ、実際この順番で毎年出題されているので、普通に問題を1ページ目から順番に解いていけばいいんですけどね笑
詳細な勉強法は以下の記事にまとめましたのでよかったら参考にしてください。
公認会計士試験の科目別勉強時間⑥選択科目
公認会計士試験は2次試験である論文式試験に、民法、経済学、経営学、統計学の4つから選択する選択科目があります。
この4つの必要な勉強時間は以下です。
民法 400時間
経済学 300時間
経営学 200時間
統計学 200時間
民法と経済学はとても勉強量が多いです。
ですので選択科目は8割の人が経営学、理系で数学に自信がある方は統計学を選択します。
経営学は公認会計士論文式試験に合格した後に受験することとなる終了考査でも同じような科目があり、そこにもつながるので、やはり選択科目としては統計学がおすすめです。
ただ、私は理系で数学が好きなので統計学を選択しました。ですので経営学の勉強法について解説することはできません。
統計学の詳細な勉強法は以下の記事にまとめましたのでよかったら参考にしてください。
大学生が公認会計士になる勉強時間④公認会計士試験の勉強時間【他の資格との比較】

先に結論
公認会計士試験は弁護士より簡単で、社労士や司法書士よりは難しい。
ここで、公認会計士試験の勉強時間を他の資格の勉強時間と比べてみましょう。
他の資格などに必要な勉強時間は以下のように言われています。
簿記3級 50時間
簿記2級 200時間
(公認会計士の3000~5000時間にはもちろんこの簿記の勉強時間も含まれています。)
社会保険労務士 1000時間
司法書士 2000~3000時間
税理士 3000~5000時間
弁護士 6000~8000時間
東大合格 6000~8000時間
これを見ると公認会計士試験の合格に必要場勉強時間は、司法書士や社労士よりは長く、税理士と同じくらいで、弁護士や東大と比べたら短い。という感じです。
公認会計士になるのは早稲田・慶応出身が一番多く、司法試験合格者で一番多いのは東大出身なので、この数字は正しいと思います。
公認会計士になるのは難しいですが、東大に入ったり弁護士になるほどは難しくないということです。
また、公認会計士は早稲田・慶応出身が多いと書きましたが、MARCHや日東駒専の人も全然いますし、僕みたいな高卒も全然いるので安心してください。
大学生が公認会計士になる勉強時間⑤短期合格を狙う方法

先に結論
できるだけ早く合格したいのなら、予備校に入るのが手っ取り早い。
理由は、勉強に必要なものがすぐに全て揃うから。独学だとなかなか揃いません。
公認会計士試験にできるだけ早く合格する方法は、予備校に入ることです。
これは言い換えれば、「独学は避ける」ということです。
どういうことかというと、独学だと以下のような非効率が発生します。
①教材をそろえるのに時間がかかる
②授業がないので、難しい論点は自分で調べるしかない。
③質問ができない
私は独学で公認会計士試験に挑んだのですが、上記のような非効率が発生しました。
それでも費用を安く抑えたい、自分のやり方で勉強を進めたいという方は独学で良いと思いますが、とにかく早く合格したいなら予備校に入った方がいいです。
予備校に入れば必要な教材はすぐにそろって、すぐに勉強をスタートできます。わからないときはすぐに講師に質問できます。
予備校の効率的なカリキュラムに身を置く、結局これが一番効率的です。
大学生が公認会計士になる勉強時間⑥おすすめの予備校
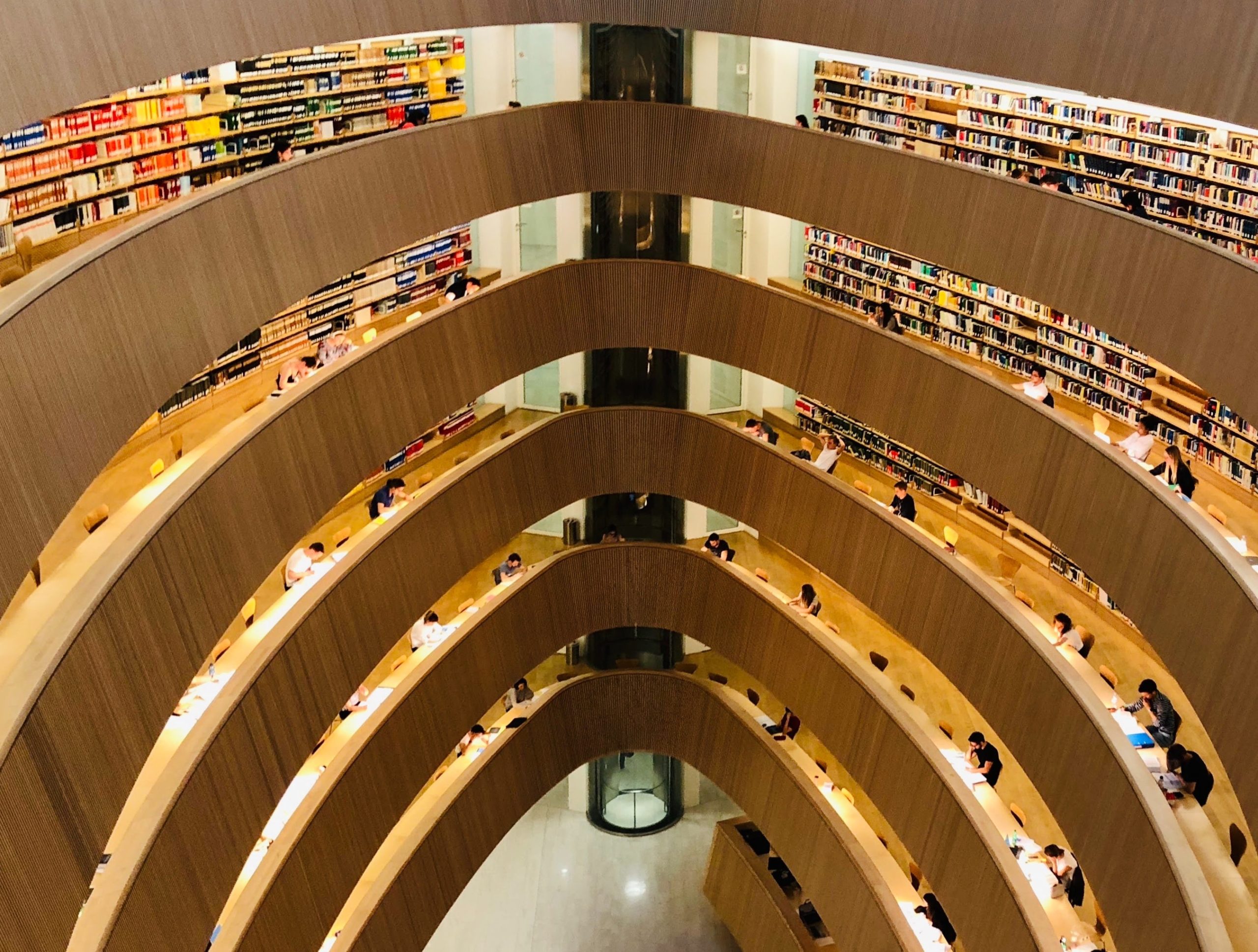
先に結論
おすすめはCPA会計学院。理由は通信コースのサポート体制が一番充実しているから。値段が気になるならクレアールもあり!
先に結論
おすすめの予備校はCPA会計学院。理由は①合格者数が圧倒的に多いから②質問へのフォローも充実しているから。
値段が気になるならクレアールもあり!
ここでは、おすすめの予備校をご説明いたします。
私が予備校を評価するうえで重要視している点は以下です。
・教材はわかりやすいか
・授業はわかりやすいか
・通信コースに対するフォロー体制
・デジタル対応
教材・授業のわかりやすさは当然ですが、こちらからの質問にしっかり答えてくれるかというのは、とても重要な点の一つだと思います。質問しても疑問が解決しなかったり、なかなか質問できない環境だと勉強の効率が落ちるので。
また、予備校に入っても学習の中心は自習になりますので、自習のしやすさ(いつでもどこでも学習できるか)と言う意味で、デジタル対応も重要な点の一つです。教材や授業がネットで見れたり、ネットから質問ができると勉強の効率が上がります。
また、学生や勉強に専念している方より勉強時間が限られる社会人の方には、やはり通信がおすすめです。理由は通学時間が省略できることと、通信のサポート体制が整っている予備校なら、通信でも通学と比べて差がほとんどないからです。
これらの点から、私がおすすめする予備校はCPA会計学院です。正直、今入学するならこの予備校一択です。また、コスパ面を重視するならクレアールです。
おすすめの予備校①CPA会計学院

| 受講料 | 60~85万 |
| 直近の合格者数 | 973名 |
| 校舎の数 | 5校 |
CPA会計学院のメリットは以下です。
驚異的な合格者数
教材・講師の質の高さ
デジタル対応が最も進んでいる予備校
通信のサポート体制が予備校の中で最も充実している
驚異的な合格者数
CPA会計学院は2024年の合格者数トップの公認会計士予備校です(2024年 合格者数973名 合格者占有率60.7%)。
公認会計士試験の予備校は、TACと大原が昔からの大手で、2015年ほどまではこの2校で合格者の大半を独占していました。
そこに近年急成長したのがCPA会計学院で、2021年に合格者数でトップに立ち、今では合格者占有率60.7%と合格者の6割を占めています。
これだけ急成長した理由としては、講師の質の高さ、教材の質の高さ、サポート体制の充実が挙げられます。詳細を以下で解説していきます。
有名講師陣
CPA会計学院は数年前に他の予備校から有名講師を引き抜いており、講師の方はみなさん公認会計士会では有名な講師です。ですので、授業の質はとても高いです。
また、CPA会計学院にはチューターという制度があるのですが、こちらもとても評判がいいです。チューターとは前年に公認会計士試験に合格した方達のことで、大学在学中に合格した方が中心のようです。
CPA会計学院の校舎には講師だけでなく、このチューターが常駐しており、生徒の質問対応をしています。前年に実際に合格しているチューターの方々は知識が新鮮ですし、自分が抱えているのと同じような悩みを必ず経験しているはずなので、そんなチューターの方々に質問できるのは、とても有意義だと思います。
教材の質の高さ
CPA会計学院の教材はとても質が高いことで有名です。私も実際にCPA会計学院の教材を使ったのですが、とても良い教材でした。教材が分かりやすく書いてあることは当然として、私が非常に助かったのが、CPA会計学院の教材には、範囲ごとにA~Cの重要性が書いてあることです。
公認会計士試験の範囲の中には、ほとんど本番で出題されないので捨てるべき部分としょっちゅう出るので重点的に勉強すべき部分があります。A~Cの重要性はその判断に使え、それは学習の効率をグンと上げてくれます。
また、この重要性は答練や模試にも書いてあるので、実際の試験で「難しいので捨てるべき問題を捨てる練習」にも使えます。公認会計士試験では「難易度が高すぎて、解こうとするととても時間がかかるし正答率も低いので捨てるべき問題」が毎年必ず出題されます。
問題を解く練習も大切ですが、問題を捨てる練習も同じくらい大切です。その練習ができるのはとても助かります。
デジタル対応
CPA会計学院は大手予備校の中で最もデジタル対応が進んでいます。具体的には以下のようなデジタル化が図られています。
・全ての教材がwebでも読める。(もちろん紙媒体の物ももらえます)
・講義は全てwebでも受講できる
・講義は音声データ版もある(電車や寝るときにイヤホンで講義を聴ける)
ここまでデジタル化されていますので、いつでもどこでも勉強できます。勉強は電車やカフェでも勉強したいという方にとって、これはとても助かると思います。
通信のサポート体制
CPA会計学院の強みとして校舎に講師が常駐しているので、いつでも質問できると記載いたしましたが、CPA会計学院は通信コースの方も講師・チューターに質問できます。
その方法は電話・メール・Zoom・バーチャル校・対面面と全ての質問方法がそろっていますので、通信でもわからないところはすぐに質問できます。
また、授業は上記のweb講義を視聴でき、教材は紙の物とデジタル教材の両方をもらえますので、通信と通学の差はほとんどないと思います。
まとめ
これら以外にも、CPA会計学院は公認会計士専門の予備校である、綺麗な自習室がある、女子専用自習ブースがあるなど環境が整いまくってます。
正直、本気で合格を目指すならCPA会計学院に入っておけば間違いないです。
CPA会計学院に入るなら、無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです。
おすすめの予備校②クレアール

| 受講料 | 45~60万 |
| 直近の合格者数 | 非公開 |
| 校舎の数 | 通信のみ |
クレアールのメリットは以下です。
受講料が安い
効率的カリキュラム
デジタル対応が充実している
いつでも回数無制限で電話で講師に質問できる
受講料が安い
クレアールのメリットは何といっても受講料の安さです。大手3校(CPA会計学院、大原、TAC)の受講料が、コースにもよりますがだいたい75~85万円ほどであるところ、クレアールは45~60万円ほど、短答式までのコースなら300,000円となっております。
「安いんなら、その分質も落ちるんじゃないの?」
このように思う方もいらっしゃると思いますが、それほど他の予備校と変わりません。私は全ての予備校のテキストを読んで比較したのですが、テキストも他と大して変わりません。また、以下に記載しているようなクレアールならではの強みもたくさんあります。
効率的カリキュラム
クレアールは非常識合格法という他の予備校とは異なる独自のカリキュラムをとっています。
その内容は、短答式の内から論文式の勉強も始める、よく出る範囲を重点的に勉強するというもので、短期合格を目指すもののようです。
公認会計士試験の特徴はとにかく範囲が広いことです。
ただ、その試験範囲の中にはほとんど試験では出題されない範囲もあります。
そのため、公認会計士試験の攻略法は試験に出る範囲を重点的に学習し、ほとんど出ない範囲はある程度捨てるという方法です。合格した人はこういった勉強法を取っており、実際、私もそういった勉強法で合格しました。
その点、クレアールの教材は最初から、試験によく出る範囲を重点的に、ほとんど出ない範囲はカットされた教材となっております。
そのためクレアールの教材を使えば自ずと公認会計士試験向けの勉強法となり、合格への最短ルートを進めると思います。
デジタル対応
クレアールは講義・教材共にPC・スマホ・タブレットすべての端末から閲覧・ダウンロード可能であり、完全にデジタル対応しています。
またそれだけでなく、クレアールは2025年合格目標コースからCROSS STUDYという独自の学習支援ツールをリリースしています。
これはオンラインで問題集が解けるシステムであり、自分だけの問題集のカスタマイズ、定期的な確認問題の配信などの機能が盛り込まれたオンライン学習ツールです。
「自分が苦手な範囲だけをまとめたオリジナル問題集をカスタマイズ」「配信される確認問題を解くことで知識の掘り起こし」など使い方は自由自在です。
これは範囲がとても広く、効率的に学習を進めることが重要な公認会計士試験にとてもマッチしたシステムであり、筆者としてはとてもおすすめできるシステムです。
フォロー体制
クレアールでは電話・メール・SNSで講師に質問可能で、電話は回数無制限です。
他の予備校では講師への質問は予約制であったり、1か月ごとの回数制限があったりするのですが、クレアールにそういったものはないのでとても質問しやすい環境だと思います。
まとめ
ここまで書いたように、クレアールはとても安いですが、とても魅力のある予備校です。
そのためコスパを重視する方にはクレアールがおすすめです。
クレアールのことをもっと知りたい方は資料請求するのが手っ取り早いです。クレアールへの資料請求は以下です。
大学生が公認会計士になる勉強時間⑦河野玄斗さんおすすめの予備校
先に結論
河野玄斗さんおすすめの予備校もCPA会計学院
理由は①合格実績②圧縮講義の効率性
みなさん、東大卒ユーチューバーの河野玄斗さんはご存じでしょうか?
東大医学部卒で医師国家試験と司法試験両方に合格していて、現在は効率のいい勉強法などを紹介されているユーチューバーです。
そんな河野玄斗さんが2022年に公認会計士試験を受験されました。
その勉強を始める際にまず予備校を選んでいるのですが、河野玄斗さんもCPA会計学院を選んでいます。その動画が以下です。
河野さんはCPA会計学院を選んだ理由として、合格実績と圧縮講義を挙げていますね。
この後、河野玄斗さんは実際にCPA会計学院を受講して、公認会計士試験に半年という超短期で合格しました。
河野玄斗さんの基礎学力は当然短期合格に寄与していると思いますが、CPA会計学院のテキストのわかりやすさ、圧縮講義の効率性も短期合格に寄与しています。
大学生が公認会計士になる勉強時間⑧まとめ

この記事では大学生が公認会計士試験に合格するまでの勉強時間について記載いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
大学の学部や専攻により、多少会計について触れている方でも、結局は3000~5000時間ほど勉強しないと合格は狙えません。
ですので、
大学で簿記等を勉強した方は、それでも合格までは多大な勉強時間が必要になる
大学で会計に一切触れていない方は、大学で会計を勉強している人とそれほど大きな差はない
と思ってください。
勉強時間については以下の記事で科目別で詳細に解説していますので、よかったら参考にしてください。
公認会計士試験の科目別の勉強時間を知りたい人、公認会計士試験に短期合格したい人向け。内容⇒簿記、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法、租税法、経営学の勉強時間etc。この記事を読めば、公認会計士試験のどの科目にどれだけの時間を書ければいいのか、どのように勉強すれば勉強時間を短縮できるのかがわかります。